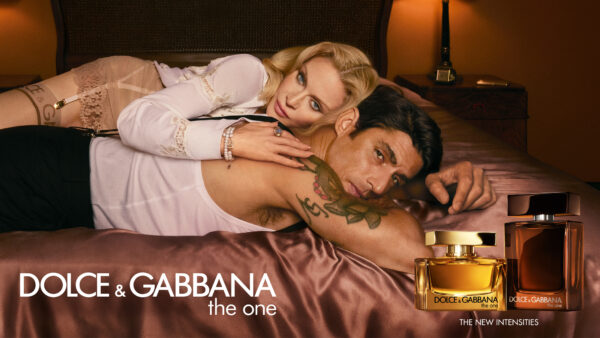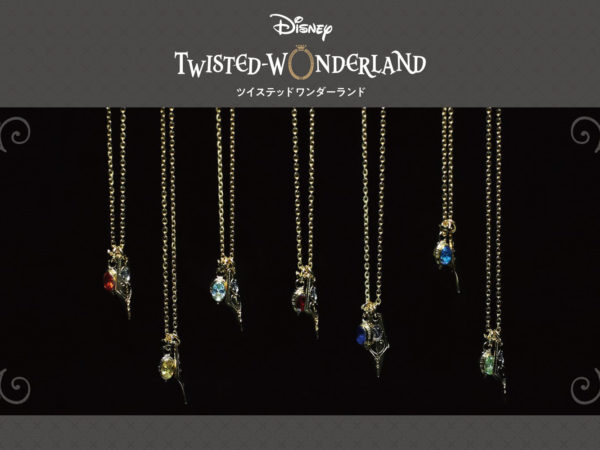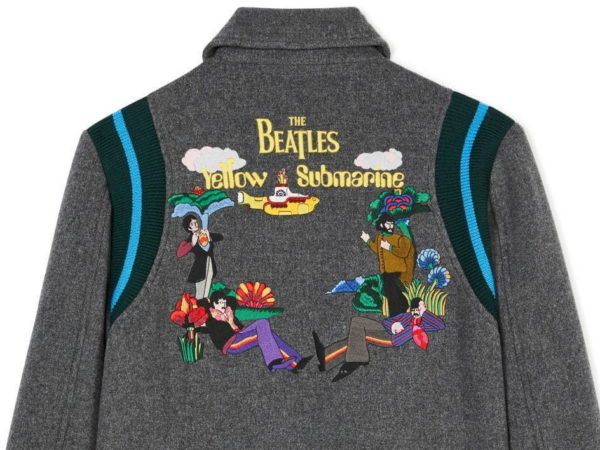地下から送る耽美で優雅な変わらないアンダーグラウンド。
ALI PROJECTが10月15日、ニューアルバム『Underground Insanity』をリリース。2025年に34周年を迎えながら、ほぼ毎年ニューアルバムをリリースし、ライブやイベントへの出演などで精力的に活動するアリプロ。今作は「アンダーグラウンド」を合言葉に、耽美で鋭く、どこか優しさを持つアリプロらしい楽曲が揃った。インタビューでは宝野アリカと片倉三起也のふたりにアルバムの制作過程を訊いた。
■まず今作のタイトル『Underground Insanity』は、直訳して「地下の狂気」ですが……。
片倉 今作は洗練されていて、ちゃんとした「音楽」にしちゃっている所があります。ただ、「アンダーグラウンド」というのは、アリプロそのものだから。僕たちが東芝でデビューした時も、その前にワンショットで出した時も、ライブに出た時も、今も、「アンダーグラウンド」がキーワードなんです。これはアリプロにとって永遠のものなんです。「カウンターカルチャー」という言葉とも似ているんだけど、もっと地下に潜り込んだようなもので。ALI PROJECTというのは、逆にわかりやすくて、僕たちにとっては神々しい言葉だったりするので、まず「アンダーグラウンドでやりましょう」ということになり、今回は「あえてこれをアルバムの枕詞にしよう」ということになりました。
宝野 あと、しばらく漢字のタイトルが続いたからというのもあります。前回も『若輩者』だったし。「そろそろ英語のタイトルにしようかな」みたいなところがありました。
■アンダーグラウンドにもいろいろありますが、アリプロの「アンダーグラウンド」は、どういう「アンダーグラウンド」なのでしょうか?
宝野 私にとってのアングラは本当は白塗りで踊っていることなんですけど(笑)、自分自身のこととなるとちょっと違うよね。(笑)
片倉 思想的なことです。
宝野 そうそう。「主流から離れている」というところ。
片倉 ポピュリズムが悪いことだとは思わないんだけど、ポピュリズムとは一線を画したもので、ポピュリズムを目指す価値を持たないのがアンダーグラウンドだと思います。かと言って、それは「人に理解されないもの」でもないんですよ。ポピュリズムとは違うものといっても、ポピュリズムは脚光を浴びるだけのものでもない。そういうものが「音楽」なんです。音楽そのものの行き詰まり感もあり、メロディはもう出尽くしちゃっている。いろんな考え方があっていいんだけど、そもそも「メジャー」という言い方も変だと思っています。
■なるほど。「作り上げられたメジャーシーンとは違うもの」という感じでしょうか?
片倉 そうかもね。でも、それを言ったらこの業界大変よ。(笑)
■そんな話を聞きつつ、曲を見ていくと“GARAKUTA”というポップな曲があるじゃないですか。
片倉 これは僕が10年くらい前に好きだったGarbageというバンドがあって、その曲調を意識しています。当時、宝野さんがアリプロ以外のバンドでやっていた曲にもこういうのがあって、「バンドをつけて歌ったら面白いかな?」なんていう妄想があったりもして。今回はGarbageが好きだったことを思い出し、Garbageの曲とは全然似ていないんですけど、そういう意味合いでこの曲を書きました。
■歌詞はもう、ストレートに?
宝野 「Garbage」は「ゴミ」という意味だから、「ゴミみたいだけど、生きている私たち」みたいな歌詞にしようかなと思い、ガラクタが散らばっている感じにしました。それで、私的に、「ガラクタ」は「我楽多」と書くじゃないですか。それが素敵だと思ったことと、私の家は我楽多が溜まっていく一方なんだけど、それでもいいじゃない……?という所から書いていきました。
■なるほど。これはリアルな曲なんですか?
宝野 そうね。「叩かれまくっても出てくるのはホコリじゃなくて矜持だ」という。私の現実そのままというわけではないですけど。
■それにしても、アリカ様の御口から「栄養士」という言葉が出てくるとは思いませんでした。(笑)
宝野 栄養士ね。(笑) 私、最近ファスティングをやってみたりしているんです。食べ過ぎると栄養士がいろいろと言うんですよ。そういうところにはリアルが入っていますね。(笑)
■そんなアリカ様がいつまでも青春でいらっしゃるのがありがたいです。さて、1曲目に戻って“Underground Mad Tea Party”ですが、タイトルを読まないまま聴いた時、なぜか『不思議の国のアリス』がモチーフだとは気づかなかったんです。
宝野 別にモチーフだと思わなくてもいいんです。ウサギと帽子屋が出てきたらイコールになるけど、「アリス」という名前は出て来ないので。
■なんというか、むしろ現実的な曲に感じました。
宝野 現実的ですよ。地下に招待されている「あなた」は、普通の子じゃなくて、いじめられっ子とか、引きこもっている子とか、そういう子なわけです。他のみんなは招待状をもらうけど、その子はもらえないわけ。でも、それこそがこの地下室のお茶会への招待状……だということです。「どんな格好をしてもいいし、誰も笑わないから、誰もあなたをいじめないから、ここに来て一緒にパーティーをしましょう」って。地上では槍が降っていたり、本当に戦争が起こっていたり、悪意があふれていたりするけれど、地下の私たちは箱船の中なのよ、これは平和なのよ、世界が終わっても大丈夫、という、そういうお茶会にしたかったんです。
■素敵なお茶会ですね。
宝野 私、普通のお茶会って苦手なんですよね。だって甘いものが嫌いなので、延々と食べていたらおかしくなっちゃう。だから、「自分がお茶会をやるならこういう感じかな?」というものを書いています。毒キノコとか、阿芙蓉とか。
■本当に面白い曲でした。そうやって聞いてからこのタイトルを読んだら、急に『不思議の国のアリス』のモチーフに染まったんです。逆に、なぜこのモチーフを今持って来たのでしょうか?
宝野 やっぱり私にとって、アリスは永遠にアリスなんです。今までもアリスを使った曲があるけれど、この曲は今までのものとは違うふうに作ろうと思って。大サビの「あなたの夢は/ユメから醒めない」の「あなた」は最初、「アリス」にしようかな?とも思っていました。でも別にしなくてもいいかなという気になって。
■ここはアリスと取る人も、自分のことと取る人もいるでしょうね。サウンドの方もストリングスがずっと動き回っている感じが面白いです。
片倉 うるさいよね?(笑)
■インタビュアーとして、「そうですね」とは言えない一言ですね。(笑)
片倉 この和声にあのストリングスは、ずいぶん斜めからぶち込んでいる感じ。ヴァイオリンの子(メンバー)が、「僕はどこを弾くんだろう?と思いながら聴いていました」と言っていましたね。(笑)
■実演時のことはあまり意識していらっしゃらないんでしょうか?
片倉 実際にこれをヴァイオリンの譜面に起こした時、ちゃんと整理整頓して作っていないんですよ。「1stがこの辺で刻みとかサスティンをやっているけど、全然違うところでもうひとりが何かやっている」という感じ。多分クラシックの作曲家や、編曲家は絶対にやらないことですよね。それが面白いんですよ。
■確かにそこが面白かったです。2曲目の“日本男子、獅子奮迅”ですが、私は勝手ながらこの系統の楽曲を「軍歌系アリプロ」と呼ばせていただいております。
宝野 やっぱり「大和魂」的なものをね。ちょっと勇ましい感じの曲が来た時には、そういうものにしますけど、これはまず「獅子奮迅」という言葉が先にあったんです。
■タイトルが「獅子奮迅」だけになる可能性もあったんですか?
宝野 そうそう。でも、書いていくうちにこうなりました。なんで「獅子奮迅」かというと、佐賀旅行に行った時、ホテルに「獅子奮迅」と書かれたユニフォームを着た少年たちがいっぱいいたんです。コーチみたいな人もそれを着ていてね。先生を見たら「柔道部かな?」と思ったんだけど、少年たちは細くて坊主頭だったので、「野球部なのかな?九州大会があるからここに泊まっていたのかな?」とも思ったりして。その子たちは田舎の子だから、東京の子と違って、スれていない感じがとても良かったんです。だから、「このまま清らかに大人になってほしい」という想いがだんだん込められていって、こういう形の歌詞になりました。
■意外にもそのホテルから出てきた歌詞だったんですね。もっと思想的な所から出てきたんじゃないかと思っていました。(笑)
片倉 アリプロはね、保守です。(笑) 僕が思うに保守というのはワールドスタンダードなんですよ。自分の国を愛する心を持つことですね。
宝野 日本を大事にしてほしいです。
■そういう心持ちは大切なことだと思います。でも、スポーツ少年の話を聞いてからこの歌詞を読み返すと、「確かにスポーツの応援歌だ」と思いました。
宝野 アリプロのこういう曲さ、甲子園のテーマソングになってもいいなと思うんだけど。でも誰も歌えないから応援にならないか。(笑)
■ブラスバンドはきっとこういう曲が大好物ですよ。
片倉 確かに地方の高校生のオケなどから、「今度の演奏会でアリプロをやります!」というご報告が時々あります。
宝野 合唱もあるよね。そういうのは大歓迎です!
■絶対に演奏するのは楽しいですよ。私もやりたいです。(笑) 宝野さんはこういった「和」っぽいワードは、語感や雰囲気としてお好きなのでしょうか?
宝野 好き。今回は「獅子奮迅」をどこのメロディに入れるかをまず考えました。サビに入れたら何回も出てくるから、全部「獅子奮迅」にするわけにもいかないので、他にも良い四文字熟語を探しました。それで「志士仁人」という言葉があって、これは清らかに育った賢い大人のことですけれど、それを入れたり。こういうふうに作っていくのは楽しいです。
■ぜひともあの獅子奮迅ユニフォームの子たちにも聴いてほしいですね。その次の“暗黒IDOL”ですが、こういうヒビ割れた始まり方が好きなんです。「これこれ!これがアリプロ!」みたいな感じで。でも、昔と比べると、ちょっと音の跳躍が減りましたか……?
片倉 よくわかりましたね!というのもね、僕が聴いていて苦しいの。(笑) ときどき過去の曲を聴くじゃないですか。宝野さんが「この曲みたいにやりたい」と送ってくれることもあるんですけど、「なんでこんな変な曲を作っていたんだ!」と思うんです。(笑) 音の跳ねがすごいでしょ?転調もぐちゃぐちゃだし。例えば441Hzで歌ってい時に、339Hzぐらいになっちゃうと、もう気持ち悪くなるくらいだし。もちろん宝野さんの音程はいいんだけど、ちょっと甘いところもあったりしてね。そういうのを聴いていると、「僕はなんでこんな窮屈な曲を作っているのかしら……?」と、ここ数年で思うようになりました。
■そういうのってありますよね。
片倉 若気の至りというかね。調子に乗って作っている時だから、次から次へと新しいアイデアがあって、ガンガンそういうのを作っていました。転調もね、実験しながら作っていたから、今聴くとすごくイヤな感じがするの。(笑) ただ、5回ぐらい聴くと耳に残っていて良いんですよ。でも、何回も自分の曲を聴いて慣れるなんて変でしょ?それと、宝野さんが歌う時に、彼女のいいところの声ってあるじゃないですか。大体全部いいんだけど、どこかを強調したい時は、やっぱり作る上でいろいろと思うわけなので。だから、そういう意味でぐちゃぐちゃな感じは少しやめようかなと思いました。
■それでこの感じになったということですね。
片倉 聴きやすすぎるでしょ?それはあなたの耳が育ったのもあるんですよ?
宝野 私もやっぱり、しばらく聴いていない曲を久しぶりに聴くと、「なんだこれ、変なの」と思うんですよ。(笑) でも、2~3回聴くと思い出すんです。忘れていてもすぐに慣れて元に戻るんですよね。
■やっぱり歌うためにインプットしているところがあるんでしょうね。今作でいうと、一番「なんだこれ?」と思った曲はどれになるのでしょうか?
宝野 “Grand Bouquet”ですね。素直すぎて。(笑) でも、素直すぎるから難しいんです。
■そのパターンでしたか。“暗黒IDOL”の話に戻って、アイドルってアリカ様の中ではどういう存在なんですか?
宝野 私、地下アイドルにあまり良いイメージを持ってないんです。というのも、「現状で満足していていいの?アイドルを目指すなら地下じゃなくて松田聖子を目指せよ!」と思っちゃうから。でも、そういう中にも「私は他の子とは違う」と思っている子もいるわけじゃないですか。その子が成り上がるための曲です。地下から這い上がって、暗黒聖子ちゃんになってほしい。そういう子がいてもいいなという曲です。
■応援歌なんですね。というか、アリカ様は聖子ちゃん派なんですか?勝手なイメージで、明菜ちゃん派っぽいなと思っていました。
宝野 聖子ちゃん派ですね。明菜ちゃん派ではないです。でも、明菜ちゃんも好きですよ。
片倉 カラオケでは明菜ちゃんも歌っていたよね。(笑) それこそ白アリ、黒アリみたいなね。
■そこはちょっと意外でした。この「スカートの下にナイフを隠してる」とかいいですよね。
宝野 でも、こういうのって昔からありがちじゃない?「ちやほやされて刺されるよりも、自分から刺せ!強くあれ!」ということです。
■アイドルへの応援歌みたいなところですね。そしてこの曲の拍子は「3+3+2」なのでしょうか?
片倉 エンジニアさんにもそう言われたんですよ。でも、僕自身は全部4/4拍子で書いてます。(笑) 歌メロも全部4/4拍子ですね。
■歌メロに関しては実際そう感じました。最初と最後が全く同じなことに意図はあるのでしょうか?
片倉 アリプロの曲はイントロがそのままアウトロになることが多いので、アリプロらしさ的なところで入れました。あと、このノイジーなサウンドを1回だけしか使わないのはもったいないなと思ったので。(笑)
■なるほど。それがあるんですね。(笑) そして“不条理劇”ですが、この不協和音とキーの不安定さがまさにプログレですよね。サビはあえてキャッチ-にしてあるのでしょうか?
片倉 これはキャッチ-だね。(笑)
宝野 これね、キャッチーですよね。しかもBメロからCメロにいく時に、あんまり音を伸ばさないんです。
片倉 前はさ、サビ前に駆け上がりがあったり、仕掛けがあったりしたんだけど、こう……そういうのに飽きちゃってさ。(笑) 数年前までは仕掛けを作っていたんですが、さすがに何百曲もやっているので、「このままスパッとサビに行った方がいいな」と思ったんです。盛り上がってサビに行くのもいいけど、いきなりサビというのも印象に残りやすいのかなって。
宝野 でも、いきなりサビだから、歌の場合はここでもっと盛り上げていきたいのに……という思いが消えなくて。まぁ「仕方ないか」と思い、その前で自分なりに盛り上がりをつけているんですよ。
■ということは、あまり作曲の方には意見を言われないんですか?
宝野 そうね。
片倉 最初は結構いろいろとやりとりをしていましたけど、今はもう理解し合って、お互いの領分になっています。「このキーじゃ歌えない」ということは、たまにありますけどね。
宝野 そればっかりはスタジオに行って歌ってみないとわからないんですよね。歌詞を書きながら歌っているのとは違うので。
片倉 スタジオに入る前に歌の練習はしていないんですよ。もちろん歌詞を書く時にメロディは聴いていますが、歌の練習というのはしないんです。それで、スタジオに入り、僕とふたりでブースに入り、まず声がどんな感じかをいろいろと調整するじゃないですか。それで「こんな感じかな?」と、2~3回練習します。それで歌詞を見ながら、「この辺をこうした方がいいかな?」というセッションを1度はします。それから10回も歌ったら、すぐ本番です。
宝野 だって、1日に2曲録るんですよ?!(笑)
片倉 コスパの面でね。(笑) でも、それはちょっと可哀想だから、今回に関しては、3日で2曲にしました。
宝野 違う違う、2日で3曲!