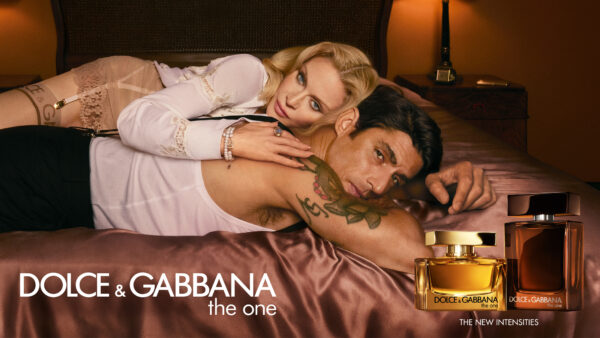■でも若干楽になった感じですね。(笑)
片倉 コーラスも全部一緒に録っちゃうんですよ。だいたい1曲につき10~12回くらい歌うのかな?でもライブでいったらセットリストの半分くらいになっちゃうか。(笑)
■ということは、1アルバムで100回以上は歌っているということですね。この歌詞はまさにシェイクスピアの「人生は舞台なり」だなと思いました。「舞台」というモチーフはこれまでもアリプロの中にありましたが、今回はどのように?
宝野 そうそう、今までもありましたね。ナントカ歌劇団とか、ナントカ劇場とか。それがあったので、今回はそうじゃないものにしたいと考えて。最初はこれ「アンチテアトル(反演劇)」というタイトルにしようと思っていたんですよ。やっぱりアングラというと、寺山修司なわけですから。今回のアルバムはアンダーグラウンドを冠しているから、前衛の舞台みたいなものをイメージして、「劇モノ」を何か入れたいなと思っていました。
■つまり最初から演劇をテーマにした曲を入れたいという想いがあったんですね。
宝野 言われてみると、そうね。だからやっぱりこれ、いろんな舞台を見ていたり、本を読んでいたり、絵を見ていたりしている人が、それぞれの劇場を思い浮かべて聴けると思うんです。今までもいろんな人がみんな別々の劇場を思い浮かべたことを話してくれて、それが面白かったです。
■ちなみにこの歌詞にあるような「心を抉りつくされて死んでしまうような音楽」を聴いてみたいですか?
宝野 それって芸術をやっている人にとっては望みというか、理想じゃないのかなと思います。でも、誰にもできないじゃないですか。「それを作りたい、作りたい……」という気持ちで今作を作れたのかなとは思っても、「いや、まだ次がある、次を作ろうよ」みたいな気持ちになりますね、たまに。
■たまに聞きますよね、あまりに理想的な作品を観てしまって、二度と作品を作れなくなってしまう人のこと。
宝野 私も前に、『天気晴朗ナレドモ波高シ』を作った時、すごく好きだったので、「もう、これでいいじゃん。もう作らなくて」と思ったんですよ。その次の『若輩者』はカバーもあったので、ちょっと楽をしたんですけど、今回またアルバムを作って、また「すごく好き!」となったのだけど、「これでいいじゃん」ではなく、「もっと作りたい!」という気持ちなの。だから、きっとまた次もいいアルバムができるんじゃないかな。そういう気持ちになったのは、やっぱりこの“不条理劇”があったからだと思います。
■とても素敵です。次の曲“地下牢から愛を込めて”ですが、最初に聴いた時、「ダンジョン」という言葉と曲調のイメージが少し合わなくて。
宝野 あら、そう?今回は「アンダーグラウンド」=「地下」ということで、私はあんまりゲームはしないけど、『ドラゴンクエスト』の地下ダンジョンで、最後の鍵を見つけるみたいなイメージを抱いていました。仲間はいたんだけど、結局ひとりになってしまい、最後の鍵を見つける。そういう歌詞にしたかったんです。
■次の“ZAZOU通りの猫オンナ”ですが、ZAZOU通りってあるんですか?
宝野 これは別にね、パリの道の名前だったらなんでもよかったんです。(笑)
片倉 簡単に言うと、第二次世界大戦中にパリにナチスが攻め入ったんですよね。そうするとフランス人の芸術家や音楽家によるレジスタンスができて、地下に潜って抵抗するじゃないですか。それで、そこでジャズを演奏したり、抵抗したりするんですよ。そういうものがあったりして、サンジェルマン通りをZAZOU通りと僕たちが勝手につけて、こうなりました。そこで歌っている女の子が「猫オンナ」です。
■言われてみるとサンジェルマン通りっぽさはありましたね。フランス語は共通テーマだったのでしょうか?
宝野 この曲はデモの段階で、Aメロにヴォイスが入っていたんです。そこに言葉が聴こえたら、その言葉を拾って使う……みたいなふうにしていて、そうしたらなんとなくフランス語になっていました。
■「出逢った時から私は女」というのは、どういう意味なのでしょうか?
宝野 私にもよくわかんないんです。(笑) それこそ不条理な感じの歌詞でいいなと思ったので、適当に書いた部分もあります。あんまり深いことを言おうとか、そういうことはしなくていいのかなと思いました。
■スキャットを入れるタイミングも絶妙ですよね。
宝野 それはね、音源のヴォイスの通りにやっています。(笑)
■確かにこれは、「耳で聴くべき曲」だと感じました。そして一番戸惑ったという“Grand Bouquet”ですが、ちょうどこの間、この曲のテーマとなった作家の展覧会がやっていましたね。
宝野 『グラン・ブーケ(大きな花束)』という絵は、常に三菱一号美術館にあるんです。これはフランスの古いお城の台所かなにかに描かれていた壁画なんですけど、お城の中にあったいくつかの絵の中で、『グラン・ブーケ(大きな花束)』だけ、日本が持っているんです。それで、もうだいぶ前ですが、それを最初に見た時に、知らずに涙が溢れてきたんです。元々オディロン・ルドンは好きだったんですけど、この絵ってすっごい大きくて圧倒されて、そのイメージを歌詞にしたらこういう曲になりました。
■この絵画って、お屋敷の中にある他の絵が美術館に送られた中、ひとつだけ残されていた絵なんですよね。それが「忘れられた/城の中の」という所で表現されていて、甘くて切ない気持ちになりました。
宝野 「もう死んじゃった懐かしい人たちが、そこにいる」みたいな感じです。コーラスも1個1個録音したんですよ。
片倉 一番多いところで6声ですね。4声のところもありますが、録音ではそれをダブルにしているからね。
■ちなみにこの曲はおふたりでテーマの擦り合わせをしたのでしょうか?
片倉 これはね、アルバムの中で最初に作った曲なんです。2024年の11月くらいから作り始めて、その時は「アンダーグラウンド」という言葉はまだ出てきていなくて。それで、まずはこういう作りやすい曲を最初に作りました。ウォーミングアップ的なところですね。それで、これがアルバムの中に入るかどうかは別にしても、「とりあえず作っちゃおう」という。だからその後が大変でした。(笑)
■そして“人形の家”ですが、タイアップ関係で「人形」をテーマとした楽曲はたくさんあると思いますが、今作はどのような形に?
宝野 そうなんですよ。いっぱいあるんですけど、今回は違う視点で作らなきゃということで、「それなら人形側の視点で書けば良いかも?」と思って。
■だから人形視点になったんですね。
宝野 これはカノンで歌うことで、もうひとりいる設定にしてあるのですが、もうひとりいるなら、役を考えなきゃいけないじゃない。(笑) それじゃあ、歌っているのが人形だったら、その「もうひとり」は、人形を可愛がってくれていた持ち主だなと思って。それで、どういう展開にすればいいかな?と考えた時、持ち主は大人になって、ある日、家出していくんですよ。でも、そこでも上手くいかなくて、孤独が募り、母の家に戻ろうと思って戻ってくるの。それを人形が待っていて、めでたしめでたし。そんなストーリーです。
■こういうのって、長く活動しているアーティストさんに対してもありますよね。一度離れていって、しばらくして戻ってきて、みたいな。
宝野 じゃあアリプロから離れている人も呼び戻さないとね。(笑)
■一度離れてしまった方も、きっとこれを聴いたらめちゃめちゃ感動すると思います。「アリプロは今もこんなに元気に活動しているんだ!」って。昔読んだ本を読んだ気分にもなると思います。拍子は6/8でいいんでしょうか?
片倉 自分は3/4で作っています。(笑) というのもね、ワルツにしたかったの。ワルツを踊りながら宝野さんが歌うミュージカルが流れてくるような。
■独特の音程の跳躍や、半音階はわざとこういう作りに?
片倉 非常にシンプルだと思うんだけどなぁ。(笑)
宝野 いや、難しいですよ!(笑) ライブで歌うのが大変だなと思っています。
片倉 でも宝野さんだったらすぐ歌えると思って。(笑) そのくらいの信頼関係が無いと、すごく平凡な曲になっちゃうし。
■なぜ最後はマイナーコードで終わるのでしょうか?
片倉 あ、確かに。なんでマイナーで終わっているんだろ?
宝野 私は間奏がマイナーで物悲しい感じだったから、「ここで待ってるわ」という気持ちかな?と思って、それに言葉を合わせたりしています。
片倉 ありがたいことです。(笑) やっぱり「バンザイ!」で終わっちゃいけないんだよね。最後にもう1回何かを感じられることを置き土産にしないとさ。2回目聴いてもらえないじゃない?
■確かに。(笑) すごく納得しました。インスト曲“out of the blue”については、まずタイトルの意味が気になって。
片倉 「晴れ渡った空から、突然なんの前触れもなく、予期せぬ素晴らしい出来事が起きますように」との希望の曲です。
■インスト曲を作る時は、何から着想されるのでしょうか?
片倉 曲を書く時って、何もないんですよ。いつもあるのは宝野さんで、宝野さんに「歌いたくない」と言われちゃったら、僕はもう作曲家じゃなくなっちゃうわけ。作曲もしたくないし。でも、唯一インスト曲というのは、これだけは絶対音楽(※タイトルがない、音楽だけを突き詰めた音楽)だから。疑わないのは絶対音楽、そういうものなわけだよね。
■なるほど、絶対音楽。
片倉 これはね、顔がないんですよ。宝野さんの声が無いからね。ヴォーカル曲は「この曲を作ったら宝野さんが怒るかな?喜ぶかな?」みたいなことは考えるし、日常のことも考えるけど、インスト曲は違う。今回は窓の外を見たら鳥が飛んでいたことから着想したんです。シベリアに住んでいるんだけど、家に大きな窓があってね、外にはちっちゃな森。そこに鳥が飛んでました。でも、鳥は羽で飛んでいるんじゃないんですよ。そこにある風が、鳥を飛ばしてくれているんです。羽で飛ぶんじゃないの、飛ばしてくれている何かがあるんだよ。それは風ですよ……というイメージ。インスト曲を作る時はそういう気分ですね。だから、最初から“out of the blue”というタイトルで作っているわけじゃないんです。後からつけました。
■本当に標題が無い、絶対音楽なんですね。そして“パラソルのある風景 2025”ですが、実に35年越しですね。ユニットの歴史を感じます。
片倉 そうだね。リリースが35年前だから、作曲しているのはもっと前になるから……まぁ、すごいよね。(笑)
■昔の音源のチューバがブカブカした感じも好きだったのですが、「2025」と冠した割に、そこまで大きな変化はありませんよね?
片倉 それには理由があるの。新しいバージョンだから、最初はオーケストラか、ジャズか、何か全く違うものにしようと思っていたのね。でも、「35年前のヘタな音源だな」と思いつつも聴いてみると、空気感がすごくいいんです。宝野さんの歌もピュアでとっても良いワケ。だからもうこれ、新しいアレンジにするのはどうも嫌だなと思い始めて。
■それで緩急が若干減った程度になったわけですね。
片倉 そう。ただね、楽器が違うのよ。というのも、同じにしたくても、当時使っていたアナログな機材をみんな処分してしまってソフト音源しかないから、35年前の音源を再現しようと思ってもなかなか作れないんです。だからチューバのブカブカも雰囲気が違うんだろうね。
■ちょっとピュアな音になっていましたね。(笑) それでは最後に、今作はリスナーにどのように聴いてほしい作品となりましたか?
宝野 そうね。ずっとアリプロを聴いている人は普通に聴けて、「また新しい感じ」と喜んでもらえると思うんですけど、久しぶりに聴く人にもすごく聴きやすいと思います。
片倉 1stアルバムの『月下の一群』を出した時のキャッチコピーが、「美しいってこういうことよ」だったんです。常に変わらないアンダーグラウンドというか、聴いてもらえるチャンスがあれば、聴いてもらえればと。10人いたら8人から9人は嫌いだと言うけど、ひとりには美しさを知ってもらえるんじゃないかな。
宝野 いろんな絵を見ていたり、舞台を観ていたり、音楽を聴いていたり、本を読んでいたりしている子は、これを聴いたらいろんなものがもっと広がって聴こえると思うので、そういう子たちにぜひ聴いてほしいです。
■素地があればあるほど面白い、ということですね。
宝野 アリプロってそうだと思います。今作のアルバムは特にね。
Interview & Text:安藤さやか
PROFILE
世界に誇るJapaneseサブカルチャーのビッグネームとして君臨し、現代アート・ミュージックを自負する宝野アリカ(作詞&ボーカル)と片倉三起也(作曲)のユニットALI PROJECT。1992年デビュー以来数々のCDを発表。数多くのアニメ主題歌を手掛けるだけでなく、定期的にオリジナルアルバムをリリース。ツアーの他、オーケストラでのコンサート『月光ソワレ』も不定期に開催。浪漫主義的“白アリ”から目眩く疾走感の“黒アリ”まで、枠に嵌らない様々な音楽形態、独特のヴィジュアルパフォーマンスで、聴く者観る者を異世界へと引きずり込む。その唯一無比のスタイルには熱狂的な支持層が存在し、国内においてはヴィジュアル系からアニメまでの幅広い層からリスペクトされる稀有な存在。芸術性の高さは海外からの評価も高い。カテゴリーされるのはアニソン、J-POP、V系のどれでもない、まさに“ALI PROJECT”というジャンルである。
https://aliproject.jp/
RELEASE
『Underground Insanity』

初回生産限定盤(CD+DVD)
TKCU-78141
¥5,800(tax in)

通常盤(CD)
TKCU-78142
¥3,100(tax in)
徳間ジャパンコミュニケーションズ
10月15日 ON SALE
LIVE
「ALI PROJECT 2025~Underground Insanity Christmas」
2025年12月25日(木) ヒューリックホール東京
[OPEN/START] 18:15/19:00